(1)どのような場合に支給されるのですか。
次の要件をすべて満たす場合、基本手当が支給されます。
1)「一般被保険者」が失業していること
2)離職の日以前2年間に「被保険者期間」が通算して12か月以上あること(ただし、「特定受給資格者」、「特定理由離職者」に該当する場合は、離職の日以前1年間に被保険者期間が通算して6か月以上ありでも可)
3)ハローワークで求職の申込みを行い、就職の意思と能力があるにもかかわらず、「失業の状態」にあること
【用語説明】
- 「一般被保険者」
- 雇用保険の適用事業に雇用される65歳未満の労働者で、「高年齢被保険者(※)」 「短期雇用特例被保険者」「日雇労働被保険者」以外の人を言います。会社に勤める正社員や週20時間以上の所定労働時間で31日以上雇用される見込みのある有期雇用契約の従業員や、パートタイム労働者などは、一般被保険者となります。
- 「被保険者期間」
- 離職日が令和2年7月31日までは、離職日から遡って1か月ごとに期間を区切り、その1か月の中で賃金が支払われた日数が11日以上ある月を被保険者期間1か月としました。改正により、離職日が令和2年8月1日からは、離職日から1か⽉ごとに区切っていた期間に、賃⾦⽀払の基礎となる日数が11日以上ある月、または、賃⾦⽀払の基礎となった労働時間数が80時間以上ある月を1か月として計算することとなりました。通常は就職日から退職日までの期間は被保険者期間となります。
- 「特定受給資格者」
- 会社の倒産や解雇など、19のケースにより失業した人を言います。再就職の準備期間の余裕がなく、保護の優先度が高いとされます。
「特定受給資格者の範囲」
Ⅰ 「倒産」等により離職した者
- ①倒産(破産、民事再生、会社更生等の各倒産手続の申立て又は手形取引の停止等)に伴い離職した者
- ②事業所において大量雇用変動の場合(1か月に30人以上の離職を予定)の届出がされたため離職した者及び当該事業主に雇用される被保険者の3分の1を超える者が離職したため離職した者
- ③事業所の廃止(事業活動停止後再開の見込みのない場合を含む。)に伴い離職した者
- ④事業所の移転により、通勤することが困難となったため離職した者
Ⅱ 「解雇」等により離職した者
- ①解雇(自己の責めに帰すべき重大な理由による解雇を除く。)により離職した者
- ②労働契約の締結に際し明示された労働条件が事実と著しく相違したことにより離職した者
- ③賃金(退職手当を除く。)の額の3分の1を超える額が支払期日までに支払われなかった月が引き続き2か月以上となったこと、又は離職の直前6か月の間に3月あったこと等により離職した者
- ④賃金が、当該労働者に支払われていた賃金に比べて85%未満に低下した(又は低下することとなった)ため離職した者(当該労働者が低下の事実について予見し得なかった場合に限る。)
- ⑤離職の直前6か月間のうちに3月連続して45時間、1月で100時間又は2~6月平均で月80時間を超える時間外労働が行われたため、又は事業主が危険若しくは健康障害の生ずるおそれがある旨を行政機関から指摘されたにもかかわらず、事業所において当該危険若しくは健康障害を防止するために必要な措置を講じなかったため離職した者
- ⑥事業主が労働者の職種転換等に際して、当該労働者の職業生活の継続のために必要な配慮を行っていないため離職した者
- ⑦期間の定めのある労働契約の更新により3年以上引き続き雇用されるに至った場合において当該労働契約が更新されないこととなったことにより離職した者
- ⑧期間の定めのある労働契約の締結に際し当該労働契約が更新されることが明示された場合において当該労働契約が更新されないこととなったことにより離職した者(上記⑦に該当する者を除く。)
- ⑨上司、同僚等からの故意の排斥又は著しい冷遇若しくは嫌がらせを受けたことによって離職した者
- ⑩事業主から直接若しくは間接に退職するよう勧奨を受けたことにより離職した者(従来から恒常的に設けられている「早期退職優遇制度」等に応募して離職した場合は、これに該当しない。)
- ⑪事業所において使用者の責めに帰すべき事由により行われた休業が引き続き3か月以上となったことにより離職した者
- ⑫事業所の業務が法令に違反したため離職した者
「特定理由離職者」の範囲
Ⅰ 期間の定めのある労働契約の期間が満了し、かつ、当該労働契約の更新がないことにより離職した者(その者が当該更新を希望したにもかかわらず、当該更新についての合意が成立するに至らなかった場合に限る。)(上記「特定受給資格者の範囲」のⅡの⑦又は⑧に該当する場合を除く。)(※)
(※)労働契約において、契約更新条項が「契約を更新する場合がある」とされている場合など、契約の更新について明示はあるが契約更新の確約まではない場合がこの基準に該当します。
Ⅱ 以下の正当な理由のある自己都合により離職した者(※)
- ①体力の不足、心身の障害、疾病、負傷、視力の減退、聴力の減退、触覚の減退等により離職した者
- ②妊娠、出産、育児等により離職し、雇用保険法第20条第1項の受給期間延長措置を受けた者
- ③父若しくは母の死亡、疾病、負傷等のため、父若しくは母を扶養するために離職を余儀なくされた場合又は常時本人の看護を必要とする親族の疾病、負傷等のために離職を余儀なくされた場合のように、家庭の事情が急変したことにより離職した者
- ④配偶者又は扶養すべき親族と別居生活を続けることが困難となったことにより離職した者
- ⑤次の理由により、通勤不可能又は困難となったことにより離職した者
- ⅰ)結婚に伴う住所の変更
- ⅱ)育児に伴う保育所その他これに準ずる施設の利用又は親族等への保育の依頼
- ⅲ)事業所の通勤困難な地への移転
- ⅳ)自己の意思に反しての住所又は居所の移転を余儀なくされたこと
- ⅴ)鉄道、軌道、バスその他運輸機関の廃止又は運行時間の変更等
- ⅵ)事業主の命による転勤又は出向に伴う別居の回避
- ⅶ)配偶者の事業主の命による転勤若しくは出向又は配偶者の再就職に伴う別居の回避
- ⑥その他、上記「特定受給資格者の範囲」のⅡの⑩に該当しない企業整備による人員整理等で希望退職者の募集に応じて離職した者等
(※)給付制限を行う場合の「正当な理由」に係る認定基準と同様に判断されます。
[具体例]―基本手当が支給されるケース
例えば、次のような場合に、新たな就職先を求めてハローワークで求職の申込みをすれば基本手当が支給されます。
- ・1年以上通常に仕事をしていた65歳未満の会社員が自己都合退職した場合
- ・6か月以上通常に仕事をしていた65歳未満の会社員が解雇されて失業した場合
- ・「契約更新する場合がある」との有期雇用契約で6か月以上通常に仕事をしていたパートタイマー(週所定労働時間は20時間以上)が、契約満了時に更新を希望したが認められなかった場合
(※)平成29年1月1日より65歳以上の労働者についても雇用保険の適用対象になりました。
(2)受給のための手続を教えて下さい。
- 本人の住所地を管轄するハローワークに、次の書類等を速やかに持参して求職の申込みを行います。
- ・「雇用保険被保険者離職票-1」
- ・「雇用保険被保険者離職票-2」
- ・「雇用保険被保険者証」
- ・「本人確認の公的書類(顔写真付)」
- ・「個人番号(マイナンバー)確認書類」
- ・「写真2枚」(サイズなど指定あり)
- ・「本人名義の預金通帳またはキャッシュカード」
※公金受取口座(デジタル庁登録済み)への振込を希望する場合は、預金通帳やキャッシュカードは不要
なお、「雇用保険被保険者離職票」(通称「離職票」)の1と2は、離職時に会社から交付されます。
「離職票-2」は「雇用保険被保険者離職証明書」と複写になっている帳票ですが、右側に離職理由をチェックする欄、右下に「離職者本人の判断」という欄があり、離職理由に異議がないかどうか、本人が○を付けて署名または捺印をする箇所がありますので、会社が記入した離職理由に間違いがないか確認しましょう。
求職の申込みを受けたハローワークは受給資格を確認した後、受給者初回説明会の案内をします。以降、その指示に従って求職活動を行い、4週間に1回ずつ直前の28日について失業の認定を受けると、7日間の「待期」期間を除き、基本手当の支給が開始されます。ただし、正当な理由がなく自己都合で退職した場合は、待期期間満了後2か月間(過去5年間に2回以上自己都合で離職している場合は3か月間)は基本手当が支給されません。
留意点
1.給付日数の計算の対象となる日は、実際に失業した日からではなく、原則として最初にハローワークに求職の申込みをした日からです。したがって、特別の事情がないにもかかわらずハローワークに求職の申込みをしないでいると、待期期間や給付制限期間以外に失業当初の給付を受けられない期間が生じるため、注意が必要です。
2.離職理由により、基本手当の所定給付日数が変わります。したがって、実際は「特定受給資格者」や「特定理由離職者」に該当するにもかかわらず、「自己都合退職」などとされた場合、本来受給できる基本手当を満額受給できない場合が生じます。この区別は、「離職票-2」の中の「離職理由」がどのように記載されているかによってハローワークが判断します。したがって、本人が当該欄に正確に記入することが大切です。
(3)基本手当は、いくら給付されますか。
1)給付額の計算
給付される金額は、次の式で計算されます。
給付される金額=「1日あたりの給付金額」×「所定給付日数」
1日あたりの給付金額:2,196円(下限額)~8,490円(上限額)
所定給付日数:90日~360日(ただし延長される場合があります)
なお、次で説明する賃金日額の区分や下限額・上限額などの金額は、令和5年8月1日から1年間の適用金額であり、毎年8月1日に見直しが行われますので、ご注意ください。
2)1日あたりの基本賃金日額
1日あたりの給付金額を「基本手当日額」と言います。基本手当日額は、働いていた時の賃金に応じて決められ、原則として離職した日の直前の6か月に毎月きまって支払われた賃金(賞与等は除く。)の合計を180で割って算出した金額(これを「賃金日額」といいます。)に給付率を乗じて計算します。この給付率は、50~80%(60歳~64歳については45~80%)となっており、賃金の低い方ほど高い率となっています。
「基本手当日額」=「賃金日額」×「給付率」
年齢別基本手当日額の計算方法
<離職日の年齢が30歳未満の場合>
| 賃金日額 | 給付率 | 基本手当日額 |
|---|---|---|
| 2,746円以上 5,110円未満 | 80% | 賃金日額の80% |
| 5,110円以上12,580円以下 | 50%~80% | 賃金日額の50%~80%(注) |
| 12,580円超 13,890円以下 | 50% | 賃金日額の50% |
| 13,890円(上限額)超 | ― | 6,945円(上限額) |
(注)y = 0.8w-0.3{(w-5,110 )/(7,470)}w
<離職日の年齢が30歳以上45歳未満の場合>
| 賃金日額 | 給付率 | 基本手当日額 |
|---|---|---|
| 2,746円以上 5,110円未満 | 80% | 賃金日額の80% |
| 5,110円以上 12,580円以下 | 50%~80% | 賃金日額の50~80%(注) |
| 12,580円超 15,430円以下 | 50% | 賃金日額の50% |
| 15,430円(上限額)超 | ― | 7,715円(上限額) |
(注)y = 0.8w-0.3{(w-5,110 )/(7,470)}w
<離職日の年齢が45歳以上60歳未満の場合>
| 賃金日額 | 給付率 | 基本手当日額 |
|---|---|---|
| 2,746円以上 5,110円未満 | 80% | 賃金日額の80% |
| 5,110円以上 12,580円以下 | 50%~80% | 賃金日額の50%~80%(注) |
| 12,580円超 16,980円以下 | 50% | 賃金日額の50% |
| 16,980円(上限額)超 | ― | 8,490円(上限額) |
(注)y = 0.8w-0.3{(w-5,110 )/(7,470)}w
<離職日の年齢が60歳以上65歳未満の場合>
| 賃金日額 | 給付率 | 基本手当日額 |
|---|---|---|
| 2,746円以上 5,110円未満 | 80% | 賃金日額の80% |
| 5,110円以上 11,300円以下 | 45~80% | 賃金日額の45~80%(注) |
| 11,300円超 16,210円以下 | 45% | 賃金日額の45% |
| 16,210円(上限額)超 | ― | 7,294円(上限額) |
(注)① y = 0.8w-0.35{(w-5,110 )/(6,190)}w
② y = 0.05w+4,520
①と②のいずれか低い方の額
基本手当早見表 【令和5年8月1日~令和6年7月31日(離職者用)】
(単位:円)
| 賃金日額 | 基本手当日額 | |||
|---|---|---|---|---|
| 30歳未満 | 30歳以上 45歳未満 |
45歳以上 60歳未満 |
60歳以上 65歳未満 |
|
| 2,000円 | 2,196 | 2,196 | 2,196 | 2,196 |
| 3,000円 | 2,400 | 2,400 | 2,400 | 2,400 |
| 4,000円 | 3,200 | 3,200 | 3,200 | 3,200 |
| 5,000円 | 4,000 | 4,000 | 4,000 | 4,000 |
| 6,000円 | 4,585 | 4,585 | 4,585 | 4,498 |
| 7,000円 | 5,068 | 5,068 | 5,068 | 4,851 |
| 8,000円 | 5,471 | 5,430 | 5,430 | 4,920 |
| 9,000円 | 5,793 | 5,793 | 5,793 | 4,970 |
| 10,000円 | 6,036 | 6,036 | 6,036 | 5,020 |
| 11,000円 | 6,197 | 6,197 | 6,197 | 5,070 |
| 12,000円 | 6,279 | 6,279 | 6,279 | 5,400 |
| 13,000円 | 6,500 | 6,500 | 6,500 | 5,850 |
| 14,000円 | 6,945 | 7,000 | 7,000 | 6,300 |
| 15,000円 | 6,945 | 7,500 | 7,500 | 6,750 |
| 16,000円 | 6,945 | 7,715 | 8,000 | 7,200 |
3)基本手当日額の下限額と上限額
また、賃金日額と基本手当日額には、下限額と上限額が定められています。これは給付率の設定のときと同じく、失業時の生活保障や就労インセンティブに配慮したものと言えます。
下限額は年齢に関わらず一律で、賃金日額は2,746円、基本手当日額は2,196円とされています。
したがって、2,746円以下の賃金日額で働いていたとしても(最低賃金法に違反しているかどうかは別問題として)、基本手当の計算の際には1日あたり2,196円で計算されます。
一方、上限額は年齢区分に応じて定められています。
| 離職日の年齢 | 賃金日額の上限額 | 基本手当日額の上限額 |
|---|---|---|
| 30歳未満 | 13,890円 | 6,945円 |
| 30歳以上45歳未満 | 15,430円 | 7,715円 |
| 45歳以上60歳未満 | 16,980円 | 8,490円 |
| 60歳以上65歳未満 | 16,210円 | 7,294円 |
4)所定給付日数
所定給付日数は、失業した理由や離職の日の年齢、「就職困難者」かどうか、そして「算定基礎期間」などに応じて、きめ細かに定められています。
【用語説明】
「就職困難者」
障害者雇用促進法に規定する障害者などを言います。
「算定基礎期間」
おおむね次の式で計算します。
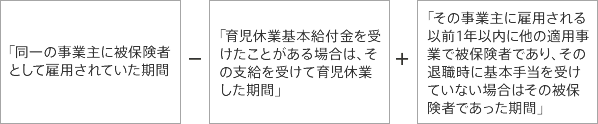
<就職困難者の所定給付日数>
|
算定基礎期間
|
|||
|
1年未満
|
1年以上 | ||
| 年齢 |
45歳未満
|
150日
|
300日
|
|
45歳以上65歳未満
|
360日 | ||
<特定受給資格者、特定理由離職者(注)の所定給付日数>
|
算定基礎期間
|
||||||
|
1年未満
|
1年以上
5年未満 |
5年以上
10年未満 |
10年以上
20年未満 |
20年以上 | ||
|
年齢
|
30歳未満
|
90日
|
90日
|
120日
|
180日
|
―
|
|
30歳以上
35歳未満 |
120日
|
180日
|
210日
|
240日
|
||
|
35歳以上
45歳未満 |
150日 |
180日
|
240日 |
270日
|
||
|
45歳以上
65歳未満 |
180日
|
240日
|
270日
|
330日
|
||
|
60歳以上
65歳未満 |
150日
|
180日
|
210日
|
240日
|
||
(注)特定理由離職者で、正当な理由により自己都合退職をした場合は、被保険者期間が、12か月以上ない人に限ります。
<上記以外の者の所定給付日数>
| 算定基礎期間 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1年未満 | 1年以上 10年未満 |
1年以上 20年未満 |
20年以上 | |
| 全年齢 | ― | 90日 | 120日 | 150日 |
(4)どれくらいの期間、受給できるのですか。
受給資格者の区分に応じて、離職の日の翌日から起算して1年~1年と60日ですが、一般的には1年間です。
したがって、失業中に特別の事情もなくハローワークに求職の申込みをしないでいると、受給期間が終了して、失業が継続しているのに所定の給付日数分を満額受けられない場合があります。
なお、病気、けが、妊娠、出産、育児等の理由により引き続き30日以上働くことができなくなった場合、その働くことのできなくなった日数だけ、受給期間を延長することができます。
延長できる期間は最長で3年間で、住所地を管轄するハローワークで所定の手続きが必要です。